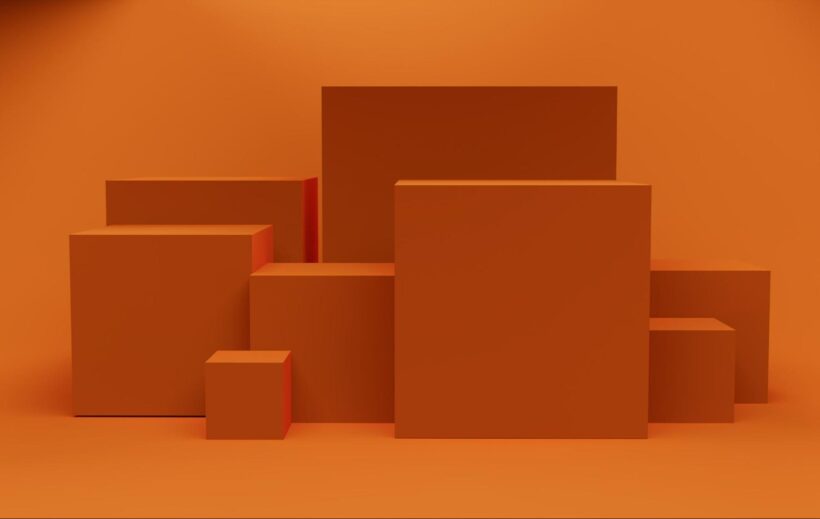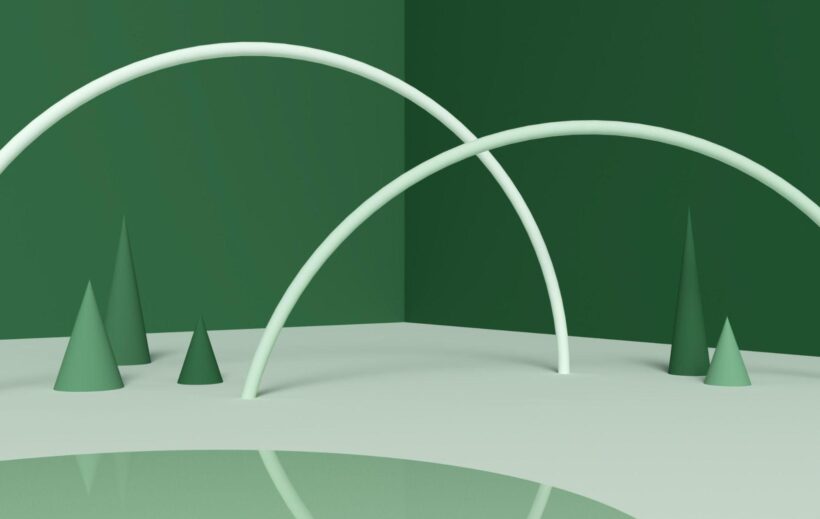Contents 目次
セラミック業界の概要と特徴
セラミックスとは、金属と非金属元素のイオン結合や共有結合で構成される無機固体材料です。化学的不活性、高融点、優れた硬度、電気絶縁性などの特性を持ち、これらの特徴が自動車、エレクトロニクス、医療、航空宇宙など多様な産業での用途拡大を促進しています。
製造工程は原料調合、成形、焼成、仕上げの過程を経て行われ、この工程により異なる特性を持つ製品が生み出されます。
セラミック業界は伝統的な窯業から始まり、現代では高機能素材へと発展。特にファインセラミックス部材は急成長を遂げ、2021年には生産総額が3.6兆円に達するなど、金属やプラスチックと並ぶ主要材料として世界市場で重要な位置を占めています。
セラミックスの種類と用途
セラミックスは伝統的セラミックスと先進的セラミックス(ファインセラミックス)に大別されます。伝統的セラミックスには陶磁器や耐火物、ガラスなどがあり、日常生活品から建材まで幅広く使用されています。
先進的セラミックスには、アルミナ、ジルコニア、炭化ケイ素、窒化ケイ素などがあり、それぞれ特有の性質を持ちます。アルミナは電子機器や医療機器に、ジルコニアは歯科材料や宝飾品に、炭化ケイ素は半導体や超硬工具に利用されています。
近年では、チタン酸ジルコン酸鉛(PZT)のような圧電材料はセンサーや音響デバイスに、フェライトは電子部品に、チッ化アルミニウムは半導体の放熱材料として産業的に重要な役割を果たしています。また、セラミックスは医療分野での応用も増加しており、バイオセラミックスは人工骨や人工関節として高齢化社会の需要に応えています。
一般セラミックスとファインセラミックスの違い
伝統的セラミックスは天然鉱物の粘土、長石、石英などを原料とし、比較的低コストで製造される陶磁器や耐火物などがそれにあたり、高い硬度と耐熱性を持つ反面、衝撃に弱く脆いという特性があります。
一方、ファインセラミックスは高純度に精製された原料や人工合成材料を使用し、精密な製造工程で作られます。アルミナ、ジルコニア、窒化ケイ素などが代表例で、製造工程では温度や圧力が厳密に管理され、高い寸法精度と性能を実現しています。
ファインセラミックスは高硬度、耐摩耗性、耐熱性に加え、優れた靭性を持ち、電子部品、医療機器、半導体、航空宇宙産業など高度な性能要求がある分野で使用されています。市場規模においても、伝統的セラミックスが従来の建材や日用品中心なのに対し、ファインセラミックスは高付加価値製品として急速に成長しています。
セラミック業界の市場規模と動向
世界のセラミック市場は、2023年に1,487億6,000万米ドルに達し、2024年から2032年にかけてCAGR7.9%で拡大し、2032年までには2,952億6,000万米ドルに成長すると予測されています。
セラミックスは製造業において金属やプラスチックと並ぶ主要材料として位置づけられ、その高機能性から産業全体の技術革新を支える重要な役割を担っています。
COVID-19パンデミックにより、2020年から2021年にかけて生産や供給チェーンに混乱が生じましたが、2022年以降は建設分野での需要回復や再生可能エネルギー分野での利用拡大により、市場は急速に回復しています。
従来は建設業界への依存度が高かった市場構造も、現在は医療機器、自動車部品、電子デバイスなど高付加価値分野での需要が増加し、多様化が進んでいます。
参考:Fortune Business Insights|ガラスセラミックス&ファイバー/陶磁器市場
(引用日2025-3月末)
国内市場の規模と推移
日本のセラミック市場も急速に拡大しており、2025年から2033年にかけては、CAGR5.3%で成長すると予測されています。この成長は、建設分野での製品利用増加や再生可能エネルギー導入に伴う需要拡大に支えられています。
日本のセラミック産業は窯業製品と先進ファインセラミックスに大別され、特に近年はファインセラミックスの構成比が拡大傾向にあります。過去10年間の推移を見ると、ファインセラミック産業は2013年から右肩上がりの成長を続け、2018年には国内生産総額が過去最高の3.2兆円に達しました。
製造業全体に占める割合は大きくないものの、その高付加価値特性から経済的意義は大きく、村田製作所や京セラなどの企業は世界市場でも大きなシェアを持っています。
ファインセラミックスの成長性
ファインセラミック市場は、技術革新と産業需要の高まりにより急速に成長しており、アドバンストセラミック市場は2024年に1,132億9,000万ドル、2032年までには2,503億ドルに達する見込みで、CAGR10.1%という高い数値が予測されています。
用途別市場構成比では、電磁気・光学用部材が73.1%と圧倒的シェアを占め、続いて熱的・半導体関連が10.9%、化学・生体・生物・生活文化が8.3%、機械的が7.8%、汎用・その他が0.1%となっています。特に成長が著しいのは電子機器・半導体産業、医療分野、電動化が進む自動車産業で、軽量化や耐腐食性を持つファインセラミックスの需要が急増しています。
また、3Dプリンティング技術の進化により複雑形状のセラミック部品製造が可能になり、ナノテクノロジーの応用によりセラミック材料の特性が飛躍的に向上するなど、技術革新が市場拡大をさらに加速させています。2023年から2025年にかけての次世代通信技術の導入も成長を後押しする重要な要因となっています。
参考:Fortune Business Insights|ガラスセラミックス&ファイバー/アドバンストセラミックス市場
参考:内閣府|マテリアルにおけるファインセラミックスの重要性と国プロへの期待
(引用日2025-3月末)
セラミック業界の主要企業とシェア状況
セラミック業界は、伝統的な陶磁器から最先端のファインセラミックスまで多様な製品を扱い、複数の産業分野にまたがるという特徴的な産業構造を持っています。
競争環境は地域によって異なり、日本や欧米の企業が技術開発とイノベーションで主導する一方、新興国企業は生産規模の拡大で台頭しています。企業分布は、主にヨーロッパ(サンゴバン、モルガン・アドバンスト・マテリアルズなど)とアジア太平洋地域(京セラ、村田製作所など)に集中し、アジア市場が最大のシェアを占めています。
主要企業の事業戦略には、新製品開発による差別化、環境に配慮した製造プロセスへの移行、特定分野での専門性強化などの共通点がありますが、各地域の市場でのアプローチには違いも見られます。
セラミック市場の主要企業のリスト
世界のセラミック業界の主要企業としては、京セラ(日本)、村田製作所(日本)、モルガン・アドバンスト・マテリアルズ(イギリス)、サンゴバン(フランス)、イメリス(フランス)、Rauschert(ドイツ)、CeramTec (ドイツ)、コーニング(アメリカ)、クアーズテック(アメリカ)、3M(アメリカ)、Applied Ceramics(アメリカ)、マテリオン(アメリカ)、McDanel Advanced Ceramic Technologies(アメリカ)、モメンティブ・パフォーマンス・マテリアルズ(アメリカ)などが挙げられます。
日本における主要企業は、上記の京セラや村田製作所に加え、日本特殊陶業、日本ガイシ、 TOTOなどが主要企業として活躍しています。特に村田製作所は、世界シェア約4割を誇るチップ積層セラミックコンデンサ分野のリーディングカンパニーとして知られています。
大手セラミック企業の動向
先にも触れたとおり、日本の村田製作所はチップ積層セラミックコンデンサ分野で世界シェア約4割を持ち、スマートフォンや自動車用センサー市場で強みを発揮しています。2021年には岡山県に新たなセラミック原料生産施設を設立し、生産能力を拡大しました。
また、京セラはファインセラミックスから産業機器まで多角的に事業を展開し、近年はFriatec GmbHからセラミック事業を買収し、欧州市場での存在感を高めています。
海外では、ドイツのCeramTecがROCAR 3Dなど3Dプリント技術を活用した新製品開発に注力し、フランスのサンゴバンは建材分野で強いポジションを確立しています。
世界的に大きな成長が予測されるセラミック市場では、大手企業は環境配慮型製品の開発や新興市場開拓など、戦略的投資を進めています。
世界市場における日本企業のポジション
日本企業は、ファインセラミックスや積層セラミックコンデンサ分野で世界トップクラスの技術力と市場シェアを誇ります。さきほども触れたとおり、村田製作所は積層セラミックコンデンサ市場で世界シェアトップを占め、京セラはファインセラミック技術で半導体や自動車産業向け高性能部品を提供し、国際競争力を維持しています。
日本企業は電子機器や自動車向けの高機能セラミック部品で強みを持ち、中でもエレクトロセラミックスは日本企業が主導する分野です。これは長年の研究開発投資と製造プロセスでの高い品質管理に起因します。
一方で、中国や韓国企業の台頭により汎用品市場での競争が激化しており、日本企業はグローバルな生産拠点展開と現地市場向け製品開発を進めています。自動車の電動化や5G通信の普及により、今後も電子部品用セラミック需要は拡大が見込まれています。
セラミック業界が直面する課題
セラミック業界は現在、複数の重要な課題に直面しています。環境規制の強化により、製造過程でのCO2排出削減や廃棄物リサイクルへの対応コストが増加し、また原材料価格の変動も利益率を圧迫する要因となっています。
グローバル競争の激化、特に低コスト生産が可能な国からの参入により、日本や先進国のメーカーは価格競争に苦しんでおり、先進的セラミックスは高性能ながら高価格であるため市場拡大が制限され、より低コストの製造技術の開発が急務となっています。また、技術革新の必要性も高まっており、環境負荷を減らすためのメタネーション触媒技術などの開発が求められています。
これらの課題に対応するため、業界全体で製造プロセスの効率化、リサイクル技術の向上、代替材料の開発など、持続可能な取り組みが進められています。
環境問題への対応
セラミック製造過程は高温焼成が必要なため、エネルギー消費量が多くCO2排出量も相当量に達しているため、環境負荷の低減が急務となっています。
近年の環境意識の高まりにより、消費者や企業はリサイクル可能で毒性のないセラミック製品を選択する傾向が強まっていますが、セラミックスは品質を失うことなく繰り返しリサイクルできる特性があり、環境への貢献が期待されています。
また、各国での環境規制強化に対応するため、企業は高効率な炉の導入や再生可能エネルギーの利用、製造プロセスの見直しなどを進めています。特に、伊藤忠セラテックが開発を進めるメタネーション触媒技術など、CO2削減とエネルギー効率向上を目指す技術革新が注目されています。
企業は環境に配慮した原材料選定や製品ライフサイクル全体を通じた環境負荷低減にも取り組んでおり、環境技術の革新が市場競争力の維持に不可欠となっています。
人材確保と教育の課題
セラミック業界では、専門技術を持つ人材の不足が深刻な問題となっています。特に、熟練工や技術者の不足は生産効率の低下を招き、企業の競争力に影響を与えています。この背景には、理科離れ現象や物づくり分野への若年層の関心低下があり、セラミック技術を学ぶ学生数も減少傾向にあります。
教育面では専門的なカリキュラム不足も課題で、多くの教育機関ではセラミック技術に関する専門教育プログラムが十分に整備されておらず、実践的なトレーニング機会も限られています。そこで業界では、人材育成のために企業内研修プログラムの充実や、熟練技術者から若手への技術継承の仕組み作りに取り組んでいます。
また、地域の産業界と連携した教育の重要性も認識され、地域特性を考慮したカリキュラム整備が進められています。大学や研究機関でも、実践的なインターンシップや産学連携プロジェクトを通じて、理論と実践の両面からセラミック技術者の育成を図っています。
セラミック企業の今後の展望と成長戦略
世界のセラミック市場が急速に成長する中、セラミック企業は明確な成長戦略の構築が求められています。成長の鍵となるのは、医療・自動車産業での需要増加、建設業界の回復、そして環境配慮型製品です。
企業はプレゼンス確立のため、バリューチェーン全体の最適化を進め、原材料調達から最終品製造までの一貫した品質管理と効率化に取り組んでいます。
新市場開拓では、アジア太平洋地域を中心とした新興市場への参入や、異業種とのパートナーシップによる新しい応用分野の創出が重要な戦略となっています。
研究開発の方向性
セラミック業界の研究開発は、基礎科学から応用技術まで幅広い分野に及んでいます。特に注力すべき研究分野には、耐熱・高強度材料などの基礎科学、燃料電池や蓄電デバイスといった新エネルギー分野、半導体関連材料の電子・情報分野、医療用インプラントなどの生体関連分野、環境浄化触媒などの環境保全分野があります。
技術面では3Dプリンティングの活用が急速に進んでおり、複雑形状の製造が可能になったことで、製品設計の自由度が大幅に向上しています。さらに、ナノテクノロジーを活用した微細構造制御も進み、従来のセラミックスでは実現できなかった特性を持つ材料開発が可能になっています。
また、産学官連携では、各地の大学や公的研究機関と企業の共同研究が活発化し、基礎研究から実用化までの橋渡しが進んでいます。競争力強化に向けた研究開発投資は、特に医療分野のバイオセラミックスや環境負荷低減技術に重点が置かれている状況です。
国際競争力強化のための戦略
日本のセラミック企業が国際競争力を強化するには、高度な技術力を活かした高付加価値製品の開発が重要です。
市場の大きさを見ると、インフラ開発や医療サービスの向上に伴いアジア太平洋地域が最大で今後も高い成長が見込まれています。一方、北米市場は技術革新を重視し、ヨーロッパでは特にドイツやフランスでエレクトロニクス産業向けの需要が拡大。南米や中東・アフリカでは建設分野での基礎需要が高まっています。
この多様な市場に対応するため、日本企業はグローバルな生産拠点の最適配置と現地ニーズに合わせた製品開発を進めています。また、国際的な研究機関との交流やグローバル人材の育成も、競争力強化の重要な要素となっています。
セラミック業界の未来技術と可能性
セラミック業界の未来技術は、高機能性と持続可能性を両立させる方向に進化しています。
特に注目されるのは環境対応型の高機能材料で、自己修復機能や外部刺激に応答するインテリジェントセラミックスの開発が進んでいます。これらの次世代材料は、自動車部品の軽量化による燃費向上や、医療分野でのバイオセラミックスの性能向上に貢献しています。
また、3Dプリンティングやナノテクノロジーの進化により、従来は不可能だった複雑形状の製造も実現し、製品設計の自由度が飛躍的に向上しています。
これらの技術革新は産業構造を変革するだけでなく、環境問題やエネルギー効率向上などの社会課題解決にも貢献し、異分野との融合により新たな価値創造を生み出しています。
ナノテクノロジーとの融合
ナノテクノロジーとセラミックスの融合は、材料性能を飛躍的に向上させる革新的アプローチとして注目されています。
ナノレベルでの構造制御により、従来のセラミックスでは実現できなかった特性を持つ材料開発が可能になり、高い強度と靭性を両立させた構造材料や、優れた電気・磁気特性を持つ機能性材料が生まれています。
特に、自動車や航空宇宙産業向けの高性能部品開発では、ナノセラミックスの微細構造制御により強度や靭性が大幅に向上し、軽量化と耐久性の両立が実現しています。また、有機・無機ハイブリッド材料の研究も進み、セラミックスと高分子材料を分子レベルで複合化することで、柔軟性と耐熱性を兼ね備えた新素材が開発されています。
製造プロセスにおいても、ナノ粒子を精密に制御する技術が進化し、原料粉の合成から後加工に至るまで全工程を見直すことで、欠点を克服する基盤技術の確立が期待されています。これらの技術革新により、効率的で環境負荷の低い製造プロセスが実現し、次世代のファインセラミック産業の競争力強化につながっています。
持続可能な社会への貢献
セラミックスは、持続可能な社会構築に多面的に貢献しています。環境分野では、CO2回収技術やメタネーション触媒など、カーボンニュートラル実現に向けた技術が注目されています。
エネルギー分野では、固体酸化物燃料電池(SOFC)や蓄電デバイスの開発が進み、再生可能エネルギーの効率的利用を支えています。
自動車向けには、軽量で高効率のセラミックコンデンサや絶縁体が開発され、電動車両のエネルギー効率向上に貢献しています。医療分野では、人体親和性の高いバイオセラミックスが骨インプラントや歯科材料として活用され、高齢化社会の健康寿命延伸を支えています。
これらの材料は環境に優しいプロセスでの生産が求められ、リサイクル可能な素材開発や製造工程のエネルギー効率向上も進められています。
今後は、デジタル技術との融合によりIoTを活用した製造プロセスの最適化や品質管理の向上が進み、廃棄物削減やエネルギー使用の効率化がさらに加速すると期待されています。
まとめ
セラミック業界は、伝統的な窯業から先端技術を駆使したファインセラミックスへと発展し、多様な産業分野で重要な役割を果たしています。世界市場は今後も着実な成長が見込まれ、特に日本企業は高品質・高機能セラミックス分野で強いポジションを維持しています。
環境規制強化や人材確保などの課題も顕在化していますが、環境配慮型製品の開発やデジタル技術活用などの戦略で乗り越えつつあります。
さらに、ナノテクノロジーとの融合や持続可能な社会への貢献など新たな可能性も広がり、これからのセラミック産業は技術革新を通じて社会課題解決と経済成長の両立を実現する重要な産業として一層の発展が期待されます。