Contents 目次
プロフィール

東北大学大学院生命科学研究科 統合生態研究室 教授 近藤倫生氏
2001年京都大学大学院理学研究科博士課程修了。龍谷大学講師・准教授・教授を経て、2018年より現職。環境DNA学会会長、日本生態学会理事、個体群生態学会理事。日本生態学会宮地賞(2004年)、Akira Okubo Prize(2011, 日本数理生物学会・Society for Mathematical Biology)、文部科学大臣表彰若手科学者賞(2013)等受賞。
数理・統計モデルなどを利用した解析手法を用いて、「環境DNA」などの生態系関連のデータを収集して生態学的現象の本質に迫るべく理論化を目指して日々研究に取り組んでいる。
企業経営陣も注目する、地域ごとの生態系を可視化する「ANEMONE」とは
ANEMONEは、これまで大学の研究者や行政の職員、市民ボランティアたちが収集してきた国内861地域(2022年6月時点)の環境DNAをデジタルデータとしてデータベースに集約し、それを自由に使ってもらえるようオープンにしている。現在もなお国内70カ所で定点観測が続けられている。
環境DNAとは、水中や土壌中など環境中に存在する生物由来のDNA(デオキシリボ核酸)のことで、環境に残留する排泄物や粘液などから取得することができる。水中の場合は1週間ほどで分解され検出されなくなるため、環境DNAを採取することで、「採取時点で、その地域にどういう種類の生物が生息していたのか」を分析することが可能になる。
環境DNAのデータベースは、「生き物の天気図」としての役割を果たす。つまり、各地域の生態系の変化(さまざまな生き物の種類の変化、比率の増減など)を把握しながら、変化の予測をたてられるのだ。例えば、イワシやサバ、アジなどの生息数の極端な減少傾向を予測したり、その予測に応じて漁獲量をコントロールするなどが可能になる。現在、国内の魚類を中心としたデータが収集されているが、仕組み的にはそれ以外の動物や、植物にも適用可能である。
従来、地域の生態系の調査は、研究員たちにより実地で地道に行われてきた。当然、データの収集に時間や手間もかかり、かつ偏りも生じてしまう。環境DNAであれば、バケツ一杯の水から採取できるため、多種多様で大量の生物データ採取がかなうというわけだ。採水さえできれば、深海や汚染された水域などでも調査が行える。
採水量については、海水域であれば2リットル~、河川や湖水など淡水域では1リットル必要だ。採水は環境DNA調査キットを用いて行われる。シリンジで吸引して採水し、市販の密閉式フィルターで濾過した上で、DNA 専門研究機関に送付。そこで得られたDNA塩基配列データは東北大学に送付されて生物の種類の判別を行う。
「採水の作業は10分程度しかかかりません。環境DNAを用いると、調査1回当たりにかかる現場コストを抑えることができるというのは重要なポイントです」と近藤氏はその利点について述べた。また調査による環境や生物への影響も最小限になることもメリットであるということだ。もちろん、調査の目的によっては従来の他の調査・観測方法を統合する必要もあるが、広範囲における多地点・高頻度の生物多様性観測を実現した革新的ツールと言えるだろう。
ANEMONEを活用した生態系の変化予測が、ネイチャーポジティブ実現のための重要な情報となる。

海水域であれば沿岸で2L、外洋で10~20L、河川や湖水など淡水域では1リットルの採水が必要となる。


企業の経営責任として求められる「ネイチャーポジティブ」とは
2022年12月にカナダのモントリオールで、国連生物多様性条約第15回締約国会議(COP15)が開催された。同会議では、「2030年までに、世界の陸・海域において、少なくとも30%を保護すること」(30by30)などを合意事項とした。国際的会議の場で初めて、生物多様性損失への対策についての方向性が明示されたのだ。日本も一先進国の義務としてその取り組みが必須となり、2023年3月末には「生物多様性国家戦略2023-2030」を閣議決定した。
そして、COP15における重要テーマが「ネイチャーポジティブ」だ。日本語訳では「自然再興」となり、「生物多様性損失を止めて、回復軌道に乗せること」を示す。上記閣議決定においても、ネイチャーポジティブの実現を目指し、生物多様性および自然資本(すなわち「地球の持続可能性の土台・人間の安全保障の根幹」)を守り活用するための戦略を実行するとしている。まず政府がその取り組みを宣言したということは、カーボンニュートラルと同様に、民間企業の経営においてもそれを積極的に目指すべきだということになる。
生物多様性とは、「多岐にわたる種類の生物が、地球上で調和しながら存在する状態」を示す。「調和」が重要であるので、生物の種類は多すぎても少なすぎてもならず、かつちょうどよいバランスを保つ必要がある。生物多様性の「損失」というのは、さまざまな理由から地球上から一部の種の個体数が極端に減少するなどして、バランスが崩れている様を表す。その要因として挙げられるのが、人間が生活や商売をするために生き物を乱獲する、人間の居住スペースを生み出すため山林を切り開く、その地域に本来生息していなかった生き物が人間の手によって持ち込まれるといったことなどだ。
「人は、動植物から得られる食料や、きれいな水や空気など、自然に頼らなければ生きていけません。そのため自然を大切にしなければならないとは昔から言われてきたことです。加えて最近は、『ネイチャーポジティブ』の動きがビジネスにも大きく影響するということで重要視されています」――近藤氏は、民間企業の間で「ネイチャーポジティブ」というキーワードの注目度が高まる背景について、このように語り出す。人間は生態系によって提供される多くの資源とプロセスから利益を得ている。このような利益は生態系サービスと呼ばれており人だけではなくビジネスもまた自然に依存しているのだという。
「例えば、半導体を製造するためにはきれいな水が必要です。その水源は、森林の維持によってもたらされます。さらに森林は、多種多様の動植物の調和で成り立っています。つまり、森林の生態系のバランスが崩れれば森林は消滅し、水源もなくなり、半導体製造もできなくなるわけです。」(近藤氏)

ネイチャーポジティブがビジネスへ及ぼす影響は大きい。2020年に世界経済フォーラムが発表した「世界の国内総生産(GDP)のうち、過半数を占める約44兆ドルが、自然資本に依存する」というデータ(※World Economic Forum (2020). The Future of Nature and Business, p.9)があり、環境省もそれを引用しネイチャーポジティブにおけるビジネスへの影響について指摘している。
もしも人々が自然資本の保護を軽視し、ビジネスが衰退してしまうと金融や保険業界も立ち行かなくなってしまう。転じて、「自然資本の保全は、世界のGDPを大きく伸ばすファクターとなり得る」とも解釈できる。ビジネスの持続可能性を高める観点においてネイチャーポジティブへの取り組みは今後ますます重要となり、企業の資金調達にも大きく影響してくることは想像にたやすい。
「今までの経済は自然を使い、減らす側面が強かったのですが、今後は自然を増やすことがビジネスにつながる社会が来ると思います。自然の恵みを最大化させるために、自然という複雑なシステムを理解、把握する必要があります」
日本ならではのネイチャーポジティブの取り組み
約2500万ヘクタールという国土の約7割弱を占める豊かな森林に恵まれた日本は、世界でも生物多様性が豊かな国の1つである。つまり、ネイチャーポジティブの取り組みの影響が他国と比較してより大きいといえる。それをリスクとするのか、逆にベネフィットとしてとらえて動くのか――近藤氏いわく、「今の日本は、まさにその分岐点に立たされているような状態」。後者ととらえて今から理解を高めておく活動が重要となるだろう。
もう1つ、日本固有の背景として近藤氏が挙げるのが「里地里山」といった原生の自然と都市部との間に存在する自然と、そこにある田畑やため池などを灌漑や間伐などで保全しながら人々が生活してきた歴史だ。
「大雨や台風がくれば、洪水や土砂崩れに見舞われ、河川の流れが変われば、新たな草地ができ草原性の生物が住みつきます。通常、治水が発達してくるとそうした入れ替わりが起こりづらくなって森林が増加する傾向になるため、その結果として草原性の生物が減少していきます」(近藤氏)。
ところが日本では、治水が発達してきたにもかかわらず、草原性の生物が生き延びてきた。年間の耕作を通じて水を張ったり抜いたりする水田や、人が通行するためのあぜ道が、草原性の生き物の生活環境を整備することにつながっていたからだ。
「欧州では、人が手を入れずに原生的な自然を保ってきた歴史があります。そのため人の活動が生物多様性を損なわせるという研究結果が目立ちます。逆に日本では、人の活動によって維持されている生物多様性があり、これらを抑制してしまうことがリスクとなり得ます」日本ならではの自然保全の取り組みを研究し、この豊かさを武器にしていくことが大事であると近藤氏はいう。
コイから始まる環境DNAとANEMONEの誕生
近藤氏の、環境DNAや生態学とのかかわりの原点は、子ども時代にありそうだという。
「小学生ぐらいの頃、『いろいろな生き物が一緒にいる』という状態が好きだったんです」――自身の研究の原点となるエピソードを振り返る。近所の原っぱに遊びに行っては、カナヘビやバッタを捕まえ、自宅で飼育し、自分が創る「小さな世界」を眺めるのを楽しんでいたそうだ。
捕獲した生き物たちに長く生きてもらえるようにすることは非常に難しいことだ。給餌や給水、温度や土など環境を整える必要がある上、個体を増やすと共食いをしてしまうこともある。虫かごや水槽という非常に小さな空間ですら、「生きる」ためのバランスを取ることは、難しく、複雑だ。幼少期には生き物を飼った経験のある人は多いと思うが、哲学的にそうしたことに思いを巡らせるわけでもなく、憶測で体験的に学ぶものだろう。
小さな世界を楽しむ少年であった近藤氏は、やがて生態系が乱れる要因や食物網の変化、生物間の関係性の影響などを理論で予測する研究にかかわるようになる。そのような研究をしていく中では、理論が正しいかどうか、実現象とのすり合わせも行わなければならない。しかし、それは「非常に難しいこと」と近藤氏は言う。生物の種類も環境も多岐にわたり、しかも常に環境は変動し続けている。フィールドから十分なデータを採取して検証することは現実的ではない。
「多種な生き物がつながりを持つほど、理論的には不安定になるといわれます。例えば、個体数の変動の激化や、絶滅の発生しやすさといったことです。しかし『豊かな自然は、維持しづらい』という理論がありながら、現実世界では実際、維持でできているという矛盾をはらんでいます」――その矛盾に挑むべく、近藤氏は研究を進めているのだという。
そこで、「理論をシミュレーションする手段はないか」と模索していた2012年、京都大学の同窓生で当時はコイの研究をしていた神戸大学の神戸大学大学院人間発達環境学研究科(現・教授)の源 利文氏から、「飼育しているコイの水槽からDNAがたくさん出てきて、調べたらそれがコイのDNAだった!」という話を聞く。
「それを、私の携わる生態系の理論化のデータとして役立てることができるのではと源君から提案されました。それで、『面白い!僕も支援するから真剣に研究しよう』と始まったのが環境DNAの研究だったんです」

2013年から、科学技術振興機構(JST)の公募プロジェクト型研究「CREST」として、ANEMONEの原点となる研究を開始。そこでは、生物多様性の保全、生物資源の管理、環境変動への適応というテーマを掲げ、調査海域の海水飼料から採取した環境DNAを活用した海水中の魚類の生態系モニタリング手法「MiFish」の開発を行った。
約5年半のCRESTプロジェクト終了後は、その調査に関心を持った企業や行政も多く他の研究費プログラムで環境DNA研究や観測網を継続することとなった。2019年には、環境DNAを用いて漁場の磯焼け(魚類たちのエサになる海藻が急に繁殖できなくなくなる)の原因究明を行った。当時の南三陸沿岸で起きていた磯焼けは、漁場に昔からいるはずのウニたちがなぜか急に海藻を食べつくしてしまうという、生態学的にいえば「レジームシフト(生態系の構造転換)」という現象だ。それは陸上でもあり得ることだ。そのようなレジームシフトを台風の進路のように予想できたらと、「生物の天気図のような、環境DNAの観測網を作ろう」という発想にいたったという。それが、ANEMONEだ。
時期を同じくして、ネイチャーポジティブや「30by30」といった取り組みが話題となってきていた。そのような社会の動きと近藤氏が研究者として取り組んできたことがリンクして研究を大きく前進させるための機運がめぐってきたというわけである。
普及の鍵は、世界中で「選ばれるビジネス」になること
ANEMONEは先も説明したように、現状では魚類のデータが中心であるが、今後はデータの種類や採取地域を拡大していく計画になっている。また現状では、データ活用も国内地域ごとにとどまっているが、採取地域は国内だけではなく世界で展開して国際的なネットワークに発展させることを目指す。直近では、既に環境DNA学会がある韓国、オーストラリア、ニュージーランドから観測体制を拡大しようと準備を進めている。
「企業がANEMONEを活用してネイチャーポジティブを目指していくとなれば、バリューチェーン全体で効果を図っていくことになるため、データは世界中で取っていくべきです」(近藤氏)
アジア地域は、日本と同様に生物多様性に富んでいることから、観測拠点として重要であるが、東南アジアはまだ環境DNAの技術研究が進んでおらず、学会も立ち上がっていない。そのため、学会のある上記地域から取り組みを開始し、そこで得た知見を東南アジア各国に展開していく計画であるとのことだ。
現在、「ANEMONE」を活用して自然共生社会の実現を目指す団体「ANEMONEコンソーシアム」は、34社・団体が参加。企業や自治体からのANEMONEに関する問い合わせも増加しているという。民間企業の業種は、海運や水産の他、化学、通信、インターネット、監査などさまざまだ。既に生物多様性など自然関係の調査を実施しているなど、今後の未来をしっかりと見据えた参加企業が目立つという。
「ネイチャーポジティブを達成するため、消費者や投資家など『お金を動かしている人たち』が、ネイチャーポジティブなビジネスや商品、サービスを『選ぶ』ということをしないといけません」と近藤氏は言う。
今、東北大学主導での、「ネイチャーポジティブ発展社会実現拠点」の立ち上げ準備を、民間企業・団体、地方自治体などと協力しながら進めている。近藤氏は、ネイチャーポジティブ実現の重要なカギが、「インターネットの活用」であると考えているという。近藤氏は、それをIoN(ネイチャーのインターネット)と表現する。複雑で予測困難な自然環境の変化をデジタルの力で予測可能にし、自然環境と人間社会のビジネスを調和させ発展させるべく、人間活動と自然とのつながりを示すデータを可視化して誰でもネイチャーポジティブについて評価できる仕組みを整え、地域住民が自然の自治管理に活用できるようにすることを目指すということだ。
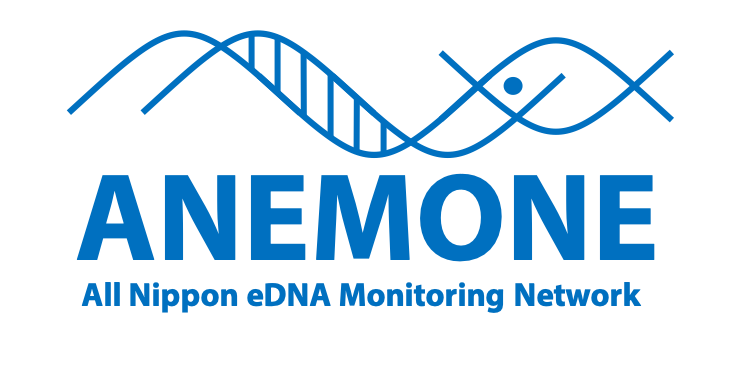
ANEMONE(All Nippon eDNA Monitoring Network)
「環境DNA」を利用した生物多様性観測ネットワーク(観測網)
https://anemone.bio/




