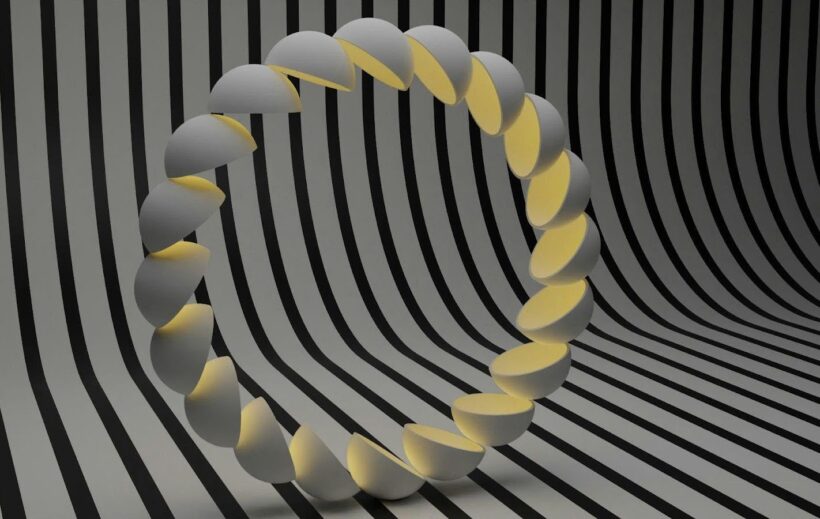Contents 目次
サービスドミナントロジックとは
サービスドミナントロジック(以下:S-Dロジック)とは、企業はモノとサービスを区別することなく一体として捉え、企業と顧客がともに価値を見出そうという理論であり、フレームワークとは異なります。
この理論は、アメリカのマーケティング研究者であるロバート・F・ラッシュと、スティーブン・L・バーゴ(以下、Vargo & Lusch)によって提唱され、論文「Evolving to a New Dominant Logic for Marketing」が、「Journal of Marketing」誌へ掲載されたことによって世界に広まりました。
具体的にS-Dロジックは、一般的なサービスとは異なり、すべての経済または経営活動をサービスとしてとらえる考え方です。
例えば、おしゃれで美味しい洋食を提供してくれる飲食店は、コース料理という商品自体の価値だけでなく、店内の装飾や店鋪の外観、また接客におけるサービスなどを包括した価値を創造するということを意味します。
従来のマーケティング手法との違いは?

S-Dロジックを充分に理解するためには、対象的な考え方であるグッズドミナントロジック(以下:G-Dロジック)とセットで把握するとイメージが湧きやすいでしょう。G-Dロジックとは、従来のマーケティングの考え方で、グッズ(モノ)そのものに価値があって、企業はそのモノを生産して顧客へ提供し、顧客はそれを消費するという考えです。
例えば、以下のようものがあげられます。
- 飲食店:おいしい食事やお酒などのドリンク
- スーパーマーケット:新鮮な食材やおいしい調理品、日用雑貨
- ゴルフ場:手入れの行き届いたきれいなコース
- 百貨店:おしゃれな洋服、装飾品、高級食材
しかし、これらの考え方は、時代の変遷やテクノロジーの進歩に対応しづらいため、急激な市場の変化によって淘汰されてしまう可能性があります。
例えば、車が普及したことによってローカルの鉄道会社が赤字となる路線が多くなったり、VODサービスが広まったことよりDVD屋のニーズが減ってしまったりというケースです。
したがって、時代の流れや市場の変化によって、それまで必要不可欠であった商品(モノ)がサービスへ変貌することもあるため、顧客が求めるニーズも変わり、それに合わせた対応をしていく必要があります。
サービスドミナントロジックの5つの公理
現在、S-Dロジックには考え方の中核となる5つの公理と11の基本前提が存在します。
考え方の特徴は、以下になります。
- 商品は、顧客が活用してはじめてその価値をもつ(=利用価値・経験価値)
- その価値は、それぞれ違った背景をもった顧客によって判断される(=文脈価値)
- 顧客は自発的であり、顧客とともに価値が生み出されるものである(=価値共創)
また、11の基本前提は2004年から徐々に内容が変化しており、最新の基本前提をそれぞれ以下の表にまとめました。
【S-D ロジックの基本的前提(FP)の発展(表-1(仮))】
| FPs | 内容 |
| FP1 (公理 1) | サービスが交換の基本的基盤である |
| FP2 | 間接的な交換は、交換の基本的基盤を見えなくしてしまう |
| FP3 | グッズはサービス提供のための伝達手段である |
| FP4 | オペラント資源が、戦略的ベネフィットの基本的源泉である |
| FP5 | すべての経済がサービス経済である |
| FP6 (公理 2) | 価値は受益者を含む複数のアクター達により常に共創される |
| FP7 | 価値を提供できないアクターは、価値提案の創造や提示するしかできない |
| FP8 | サービス中心の考え方は元来、受益者志向的であり、かつ関係的である |
| FP9 (公理 3) | すべての社会的や経済的アクターが、資源統合者である |
| FP10(公理 4) | 価値は、常に受益者が独自に現象学的に判断される |
| FP11(公理 5) | 価値創造はアクターが創造した制度、制度配列を通じて調整される |
また、5つの公理について、以下で詳しく解説します。
公理1:サービスが交換の基本的基盤である。
公理1は、サービスが交換の基本的基盤であるとされています。ここでいうサービスとは、いわゆる無形商品としてのサービスとは異なり、何らかの価値の提案から、それを受ける側へもたらされる効果や利益を指します。つまり、モノや商品の価値は不変ではなく、常に顧客の状況との文脈的価値に意味が存在していることを指します。
例えば、雨が降っている日には傘が必要であり、夏の暑い日にはうちわが欲しくなるという状況がわかりやすいのではないでしょうか。モノは、どんな状況下でも顧客が求めているわけではないため、晴れていれば傘はいらず、寒ければうちわは必要ないのです。
しかし、この考えはすべてのサービスに当てはまるとはいえません。保険や医療や娯楽などの無形サービスについては、当てはめられないため同じ分類としないよう注意が必要です。料金が発生するトリガーが人の病気や死、また娯楽はギャンブルの勝敗が価値のきっかけとなるからです。
公理2:顧客は常に共同生産者である。
S-Dロジックの提唱する行為者(企業)と顧客が価値を生み出すこととは、行為者が価値を提案するだけでは価値を創造できないとしています。また、提案を受け取る過程で価値が生まれるといっても、それは価値の提案がなければ成立しません。
つまり、価値は常に提案者と顧客の両方が存在することで生まれるため、常に共同生産者の関係であるとされています。
例えば、新車を購入した場合、顧客は車検などの管理を自身で行い、約10年後には売却してまた新車を購入するこれまでの常識を、サブスクリプション型のビジネスがくつがえしました。車の管理費などは月額に盛り込まれていて、乗りたい期間だけ契約できるため、生活環境に応じて解約もできれば、他の車種への乗り替えも可能という価値を提供しています。
これは、車の所有を求めていない顧客層を対象とし、好きな時に解約できることや管理の手間をなくせるという提案を享受して成り立っているサービスと言えます。
公理3:すべての社会的および経済的アクターが資源統合者である。
組織は、保有している専門的な強みを市場が求めているサービスへ統合して、変換するために存在します。また資源統合者とは、供給者が提供した資源と受益者が提供した資源の両方を統合することで、価値が創出されるとしています。
つまり経済とは、組織やお金、有形財を、ネットワークによって交換するための中間媒介物であるとして、組織や家庭、個人は、他の経済とともに価値を共創する資源統合者として捉えることができます。
企業は、社内において専門化を図ることでより専門性が増します。それは、オペラント資源(自ら効果を生み出す資源)から、アウトソーシングや適用的なオペラント資源の交換への移行といえます。
こうしたことから、ネットワークを通じたオペラント資源統合の考え方が読み取れます。
公理4:価値は常に受益者によって独自にかつ現象学的に判断される。
価値の創造は、顧客自らの知識やスキルを使用している現場で生まれるものです。G-D ロジックは、モノの機能面における顧客の利益を見出す一方で、S-D ロジックは、独自で現象学的なベネフィットとして判断されます。
例えば、自動車の価値が発生するタイミングは、顧客が自動車を利用する時であるため、自動車メーカーと顧客は価値を共創しているとされています。自動車メーカーは知識とスキルによって車を生産し、顧客は生活の中で自動車を使用する際に知識とスキルを適用するのです。
つまり、価値は共創されるだけではなく、他の資源との統合状態に左右されるのです。
公理5:価値創造はアクターが創造した制度や制度配列を通じて調整される。
公理 5は、さまざまな登場人物の関係性を通じて生まれる価値創造が、明確となった制度や制度配列を通じて、共有されている価値観、言語によって調整されるとしています。
このような制度によって、調整されたサービスの交換がサービス・エコシステムと称されます。そのサービス・エコシステムを、共通な制度のロジックとサービスを交換した、相互的な価値創造によって結びつけられた、資源統合アクターからなる総体的に自己完結的で自己調整的なシステムであると規定しています。
サービスドミナントロジックの身近な事例

ここでは、サービスドミナントロジックの具体例について、普段目にする商品や製品に関する身近な例を複数解説します。
何社か共通している事例は、企業と顧客との共同生産によって価値を創出したケースがありました。また、やはり競合他社が実現していない新しい価値を見出している企業も複数見受けます。
それぞれ、見ていきましょう。
無印良品:素(そ)のままポテトチップス
ポテトチップ市場における競争は、味の濃さや種類の豊富さを強化する方向に進んでいました。そんな中、2008年に無印商品は、味つけをしない、じゃがいも本来味だけで商品を販売しました。それと同時に、コンソメや黒こしょう、カレーなど8種の(味付けパウダー)を発売し、味や濃さを顧客が自分の好みで調節できるようにしました。
さらに、商品の発売とともに、Webサイト上に商品の新しい食べ方を顧客が投稿できる仕組みを設けました。それにより、顧客は「うどんのだしをつけている」など、地域特有のさまざまなアイデアが集まりました。
このような、顧客参加型の製品開発は、まさにS-Dロジックの理論に沿った施策であると言えます。企業側が用意した未完成の商品を市場に投入し、顧客と共同で価値を創出していくという事例です。
NIKE:Nike Run Clue
ナイキが展開するNike Run Clueは、ランニング記録をアプリで計測・管理を行い、SNSに投稿できるサービスです。
スマホのGPSにより、顧客が通ったルートや走行距離が記録可能なので、履歴を分析してランニングの質の向上を図ったり、走行記録をSNSで共有できるため他人と競争したりできるようにしました。これは、顧客にとってランニングの価値を高める施策が工夫されています。
また、アプリでは自身が履いているシューズを登録すれば、シューズ毎の寿命と走行距離を管理できるようになっています。ナイキは、シューズの販売だけでなく、ランニングという顧客の利用に主軸を置き、価値を創出して成功を収めています。
小松製作所:KOMTRAX
小松製作所のKOMTRAXは、建設機械の稼働状況が把握できるセンサーを自社製品に装備することで、建設機械をネットワークにつなげたシステムとして提供しました。
これにより、建設機械のさまざまなデータを分析した結果を顧客と共有することで、故障機が広い現場のどこにあるかを見つけ出すことに苦労していた課題を解決しました。
当初、供給側の製品としてオプションで売り出しましたが結果が出ず、これを標準装備として販売したところ、建設現場ごとの生産性の分析や燃料効率に関する顧客からの助言、盗難防止や車両管理などの新たな価値が生まれるようになりました。
この事例は、提供側の計画的な価値の提案ではなく、販売後、創発的におこったという事例です。
ブリヂストン:リトレッドタイヤサービス
ブリヂストンは、寿命となったタイヤのトレッドゴムという部分の表面を削って、新しいゴムを貼りつけ再利用できるタイヤのサービスの提供で成功しました。タイヤというモノを販売するのではなく、メンテナンスを中心とした「トータル・パッケージ・プラン」で、タイヤを遠隔モニタリングして状態を把握し、必要となったら新品タイヤやリトレッドタイヤの提案を行うようにしました。
リトレッドタイヤは、顧客にとっては新品の購入よりもコストをおさえられ、企業にとってはタイヤニーズの縮小傾向である市場で他社との差別化を図り、同時に顧客との継続的な関係を維持できるサービスとなり成功しました。
ブリヂストンは、自社の強みである技術と顧客価値の接合点で生まれた、サービス提供型の事業へ再構築しているのです。
Amazon:Kindle
ECサイト最大手AmazonのCEOジェフ・ベゾスは、「Kindleシリーズは本を販売しているわけではなくサービスを提供している」と言っています。
顧客が求めていることを追求した結果、エコシステムを構築してデバイスを融合させることで、顧客が閲覧したいコンテンツを簡単に見られる環境を提供したサービスがKindleシリーズです。
Kindleは電子書籍を読むためのタブレットも販売しているため、アップルのiPadが競合であると思いがちです。しかし、Kindleのアプリを無償で提供することにより、iPadでKindleを読むという端末の垣根を超えて利用できる、これまでのサービスにはなかった手法で成功しています。
LEGO:LEGO IDEAS
玩具メーカーのレゴは、レゴブロックの新商品のアイデアを世界中の顧客から収集し、ネットでそれを公開することで上位評価されたものを商品化するというプラットフォームを展開しました。
これは、顧客のセンスを商品化へ活用できるだけでなく、製品化する商品の売れ行きも想定できるため、購買数をあらかじめ予測できるというメリットがあります。
企業が販売した商品の体験方法を顧客が創作し、それが次の製品として再構築されて提供することは、まさに提供側と顧客による共同生産と言えます。
ヤマト運輸:客貨混載
このケースは、サービスの提供側2者の協業と顧客を合わせた3者による価値の創造です。
ヤマト運輸は、公共機関との連携の提案手法を通じ、地域維持と活性化に関する様々な地域サービスを実施しています。客貨混在の取り組みとして、宮崎県にある西米良村の路線バスの運用維持のため、バス会社と連携して宅配便を輸送するサービスを始めました。西米良村は面積の96%を山林が占め、老年人口が多く、生産年齢の人口割合は 50%以下と少子高齢化が進む地域です。
そんな状況下においてヤマト運輸は、座席の一部を荷台スペースとした客貨混載のバス車両を開発し、西都市と西米良村を結ぶ路線バスで宅急便を輸送するサービスを行っています。
バスで移動したいという一定数のニーズはあるものの、顧客自体の数が現象することによって、バス会社の経営が成りたたなくなります。しかし、地域維持と活性化の活動をしているヤマト運輸によって、顧客がバスに乗りたいというニーズと、企業側のバスを運行させたいというニーズをマッチさせて価値を創造したケースです。
サービスドミナントロジックを自社で活用するには

ここからは、自社でS-Dロジックを活用するときに意識しておくとよいポイントについて解説します。
これまで解説してきたように、企業は商品などのモノではなくサービスを提供することに注力しなくてはなりません。また、顧客は価値の共同生産者であるため、顧客と関連しながら、サービスの質を高めていくことが効果的な手法です。そのためには、顧客のニーズや暮らしを研究することで価値を見出すきっかけとなるでしょう。
S-Dロジックは、単なるマーケティングのフレームワークではなく、基本的な考え方としてとらえていく必要があります。そのため、決められた枠に順を追って当てはめていくだけでは答えを見出せません。顧客とともに、時にはヤマト運輸のように他業種の企業とのコラボレーションにより生み出される価値もあるのです。
サービスドミナントロジックの注意点
S-Dロジックを自社に適用する場合、いくつかの注意点があります。
- ユーザー像の普遍化・押しつけ
- データの信頼性や過度な信頼
- 目的意識と提供できるサービスの乖離
ありがちな失敗例は、自社の思いを優先してしまい、都合の良いユーザー像を決めすぎてしまったり、普遍化してしまったりするケースがあります。一人ひとり置かれている顧客の環境によって目的意識や習熟には変化があるため、そこを見すごさないよう充分注意する必要があります。
また、調査の結果にともなっていないサービスの提供を始めてしまう場合もあります。企業の想定と、顧客のニーズは必ずしもマッチするとは限りません。そのため、顧客と共同で価値を生み出すという意識を持ち続けなければ、成功までの道のりは長くなってしまいます。
まとめ
S-Dロジックは、マーケティングのフレームワークではないため、枠組みにそって分析したり当てはめたりするだけで答えが出るわけではありません。あくまで考え方であるため、自社の取り巻く環境や外部要因によって、状況は異なります。また、顧客や時には他業種の企業とのコラボレーションによって一緒に価値を創出できるケースもあります。
この記事をきっかけとして、S-Dロジックに関する取り組みをはじめられてはいかがでしょうか。