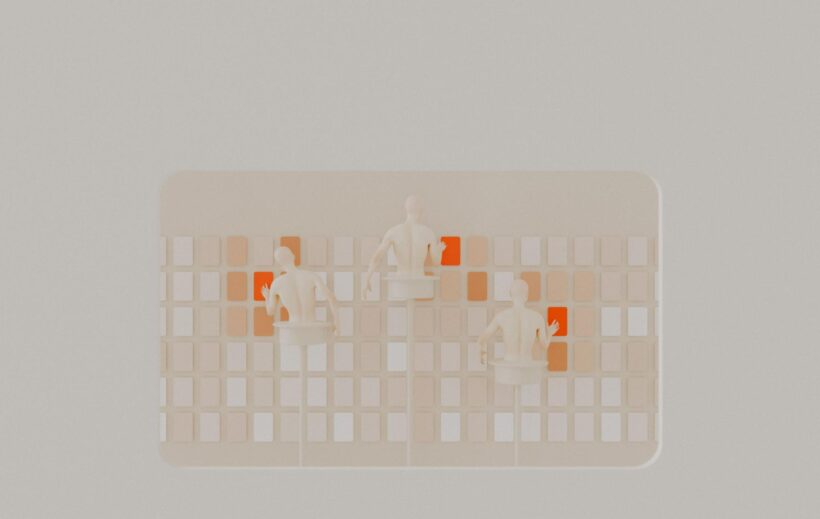Contents 目次
製紙業界を取り巻く現状と課題
製紙業界は、デジタル化の進展や環境問題への対応など、さまざまな課題に直面しています。一方で、新たな需要の創出や持続可能な事業モデルへの転換など、将来に向けた取り組みも進んでいます。
ここでは、製紙業界の現状と課題について解説します。
製紙業界の現状
製紙業界は、長年にわたり日本の産業を支える重要な役割を果たしてきました。しかし、近年はデジタル化の進展や環境意識の高まりなどにより、大きな転換期を迎えています。
紙・板紙の生産量は、リーマンショック以降、減少傾向が続いており、特に印刷用紙や新聞用紙などの需要が大きく落ち込んでいます。一方で、段ボール原紙や衛生用紙の需要は比較的堅調に推移しています。
業界全体としては、既存事業の効率化や新規事業への進出、海外展開の強化などを通じて、収益性の向上に取り組んでいます。また、環境負荷の低減や持続可能な原料調達など、ESG(環境・社会・ガバナンス)への取り組みも進めています。
デジタル化の波|紙媒体需要の減少と新たな需要の創出
デジタル技術の急速な進展により、従来、紙が担ってきた役割の多くが電子媒体に置き換わりつつあります。特に新聞や書籍、雑誌などの印刷・情報用紙の需要が大きく減少しています。
日本製紙連合会の統計によると、2010年以降、紙・板紙の国内需要は継続的に減少しています。特に新聞用紙や印刷・情報用紙、包装用紙の需要減少が顕著です。これは、スマートフォンやタブレットの普及、電子書籍市場の拡大、ペーパーレス化の進展などが要因として考えられます。
一方で、eコマースの急成長に伴い、段ボール原紙の需要は増加傾向にあります。また、衛生用紙(ティッシュペーパーやトイレットペーパーなど)の需要も堅調に推移しています。
この需要構造の変化に対応するため、製紙業界では新たな需要の創出に向けた取り組みが進められています。例えば、紙製品の用途拡大、バイオマス由来の新素材開発などが挙げられます。また、デジタル技術を活用した生産性向上や新サービスの創出にも注力しています。
参考:日本製紙連合会
製紙産業の現状 (https://www.jpa.gr.jp/states/paper/)
(引用日:2024-10月末)
原料価格の高騰と安定供給への取り組み
製紙業界にとって、原料価格の変動は収益に大きな影響を与える要因の一つです。近年、主要原料である木材パルプや古紙の価格が上昇傾向にあり、業界全体の収益を圧迫しています。
例えば、2021年以降、針葉樹パルプの輸入価格が急激に上昇しています。2021年1月には1容積トンあたり約7万円だった価格が、2022年11月には17万5,346円まで上昇しました。
この原料価格の高騰は、製紙各社の収益構造に大きな影響を与えており、多くの企業が製品価格への転嫁を進めていますが、需要が減少する中、十分な転嫁が難しい状況が続いています。
こうした状況に対応するため、業界では原料の安定供給を確保するべく、調達先の多様化による供給リスクの分散など、さまざまな取り組みを行っています。
また、代替原料の開発も進められています。非木材繊維(竹やサトウキビなど)の活用や、リサイクル技術の高度化による古紙利用率の向上などが注目されています。さらに、自社での植林事業の拡大や、サプライチェーン全体での持続可能性の向上にも取り組んでいます。
環境問題への対応|持続可能な製紙業への転換
製紙業界は、その事業特性から環境への影響が大きい産業の一つです。主な環境問題としては、森林資源の減少、製造過程での水質汚染やCO2排出、廃棄物の発生などが挙げられます。
これらの課題に対応するため、業界全体で持続可能な体制への転換が進められています。具体的な取り組みとしては、以下のようなものがあります。
- 再生紙の使用拡大:日本の製紙業界は約80%という高い古紙回収率で、資源の有効活用を積極的に推進している。
- 省エネ技術の導入:高効率設備の導入や生産プロセスの最適化により、エネルギー消費量とCO2排出量の削減を進めている。
- 森林認証制度の採用:FSC(森林管理協議会)やPEFC(森林認証プログラム)などの認証を取得し、持続可能な森林経営を推進している。
- バイオマス発電の導入:製造過程で発生する木質残渣などを燃料とするバイオマス発電の導入を進め、再生可能エネルギーの利用を拡大している。
- 水資源の有効利用:製造過程で使用する水の循環利用や浄化技術の向上により、水使用量の削減と水質保全に取り組んでいる。
これらの対応は、単なるコスト増加要因ではなく、製品の付加価値向上や企業イメージの改善にもつながっています。例えば、環境配慮型製品の開発は新たな市場開拓の機会となっており、ESG投資の観点からも企業価値向上に寄与しています。
また、森林資源の持続可能な管理は、CO2吸収源としての機能を維持するだけでなく、生物多様性の保全にも貢献しています。こうした取り組みは、国連の持続可能な開発目標(SDGs)の達成にも寄与するものとして、社会的な評価を高めています。
製紙業界の将来性と成長戦略
製紙業界は、従来の紙需要の減少に直面しながらも、新たな成長分野への進出や技術革新による競争力強化、M&Aを通じた事業ポートフォリオの転換など、さまざまな戦略を展開しています。環境負荷軽減への取り組みや海外市場への展開も、業界の将来性を左右する重要な要素となっています。
以下で、これらの成長戦略について詳しく見ていきましょう。
成長分野への注力|包装材・衛生用品市場の拡大
製紙業界において、包装材と衛生用品市場は今後の成長が期待される分野です。特に段ボール原紙の需要は、eコマースの急成長などに伴い増加傾向にあります。日本製紙連合会の統計で生産量を見てみると段ボール原紙の生産量は堅調に推移しています。
衛生用紙市場も、高齢化社会の進展や衛生意識の高まりを背景に安定的な成長が見込まれています。ティッシュペーパーやトイレットペーパーなどの需要は、コロナ禍を経てさらに拡大しています。
これらの成長分野に対し、主要製紙企業は積極的な投資を行っています。例えば、王子ホールディングスでは、東南アジアでの経済発展に伴う輸送資材としての段ボール需要の増加を受けて段ボール事業を強化しています。また、日本製紙も家庭紙事業の拡大に注力し、生産能力の増強を進めています。
参考:日本製紙連合会
製紙産業の現状 (https://www.jpa.gr.jp/states/paper/)
(引用日:2024-10月末)
技術革新による競争力強化|IoT・AIの導入
製紙業界では、IoTやAIの導入による生産性向上と品質管理の改善が進んでいます。具体的には、工場の生産ラインにIoTセンサーを設置し、リアルタイムでデータを収集・分析することで、設備の稼働状況や製品品質の監視が可能となり、生産効率の向上へとつなげています。
AIの活用も進んでおり、製造プロセスの最適化や予知保全に活用されています。設備の故障を事前に予測したりすることで、ダウンタイムの削減や品質の安定化が図られています。
これらの技術革新は、製紙業界の競争力強化に大きく貢献しています。省人化や省エネルギー化が進み、コスト競争力の向上につながっています。また、高度な品質管理により、高付加価値製品の開発や新規市場への参入も可能となっています。
M&Aによる業界再編|企業規模拡大と事業ポートフォリオの転換
製紙業界では、経営環境の変化に対応するためM&Aによる業界再編が活発化しています。例えば、王子ホールディングスは2018年に三菱製紙と資本業務提携を行いました。また、日本製紙は2019年にオーストラリアの包装メーカーから段ボール・包装部門を買収し、海外包装事業を強化しています。
これらのM&Aの主な目的は、規模の経済の追求による競争力強化や、新規事業への迅速な参入です。特に、成長が見込まれる包装材分野や海外市場での事業拡大を狙ったM&Aが目立ちます。
M&Aによる業界再編は、企業間の競争環境を変化させるとともに、業界全体の構造変革をもたらしています。大手企業による寡占化が進む一方で、特定分野に特化した中堅企業の存在感も高まっています。今後も、事業ポートフォリオの最適化を目指したM&Aが継続すると予想されます。
環境負荷軽減|脱プラスチックやCNFの取り組み
製紙業界は環境負荷軽減に向けて、脱プラスチック化やセルロースナノファイバー(CNF)の開発に注力しています。プラスチック代替製品として、紙製ストローや紙製食品容器の開発が進められており、環境配慮型製品の需要拡大に対応しています。
CNFは、木材から得られる木材繊維(パルプ)を高度に微細化した世界最先端のバイオマス素材で、軽量かつ高強度という特性を持ちます。製紙各社はCNFの実用化に向けた研究開発を進めており、自動車部品や電子機器への応用が期待されています。
これらの取り組みは、製紙業界の新たな成長機会を創出するとともに、循環型社会の実現に貢献するものです。
海外市場への展開|成長市場における事業機会の獲得
日本の製紙企業は、国内市場の成熟化を背景に、成長が見込まれる海外市場への展開を積極的に進めています。特に注目されているのは、経済成長が続く東南アジアやインドの市場です。
先にも少し触れた通り、王子ホールディングスは東南アジアでの包装事業を強化しており、段ボール加工拠点の増設を推進しています。
日本製紙も、オーストラリアなど海外での事業拡大を進めています。特に包装事業に注力しており、現地企業の買収や合弁企業の設立を通じて市場シェアの拡大を図っています。
これらの海外展開は、日本の製紙業界に新たな成長機会をもたらしています。人口増加や経済発展に伴う紙需要の拡大が見込まれる新興国市場で、日本企業の高い技術力や品質管理能力が競争優位性を発揮しています。
製紙メーカーの取り組み
製紙業界の主要企業は、市場環境の変化に対応するためさまざまな成長戦略を展開しています。王子製紙、日本製紙、大王製紙、レンゴーといった大手メーカーは、それぞれの強みを活かしつつ、新たな事業領域への進出や海外展開、環境対応など、多角的なアプローチで業界の課題に取り組んでいます。
以下では、各社の具体的な取り組みについて見ていきましょう。
王子製紙
王子製紙は、グローバル展開と事業構造の転換を軸とした成長戦略を推進しています。特に東南アジアでの包装事業に注力しており、マレーシアやベトナムで段ボール工場を展開しています。マレーシアでは段ボール製品のシェアが30%を超え、現地での一貫生産体制を構築しています。
また、環境対応にも積極的で、国内外で大規模な森林経営を行っています。国内では約18万haの社有林「王子の森」を保有・管理し、海外の保有林は約29万haに達します。これらの森林資源を活用し、持続可能な事業モデルの構築を目指しています。
日本製紙
日本製紙は、紙事業の構造転換と成長分野への経営資源シフトを進めています。特に注力しているのが海外包装事業で、先にお伝えしたとおり、2019年にオーストラリアの包装メーカーから段ボール・包装部門を買収しています。
同社は新素材開発にも力を入れており、CNFの実用化に向けた取り組みを進めています。CNFを用いた透明シートの開発に成功し、電子材料や透明表示体など、エレクトロニクス分野での利用が期待されています。また、バイオマス発電事業にも参入し、再生可能エネルギーの活用を推進しています。
大王製紙
大王製紙は、主力の家庭紙事業の強化と新規事業の育成に注力しています。特に衛生用品分野での成長が著しく、「エリエール」ブランドのティッシュペーパーやトイレットペーパーの販売を拡大しています。また、ベビー用おむつや大人用おむつなどにも力を入れています。
海外展開にも積極的で、東南アジアを中心に事業拡大を図っています。タイやインドネシアでの紙おむつ事業を強化し、現地の需要増加に対応しています。さらに、環境配慮型製品の開発にも注力しており、植物由来の原料を使用した製品ラインナップを拡充しています。
レンゴー
レンゴーは、段ボール・紙器を中心とした包装ソリューションのリーディングカンパニーとして、事業拡大を進めています。eコマース市場の成長を背景に、段ボール需要の増加に対応するため、生産能力の増強や物流の効率化に取り組んでいます。
同社は、環境負荷軽減にも注力しており、リサイクル技術の向上や軽量化製品の開発を進めています。海外展開も積極的で、東南アジアや北米での事業基盤を強化し、グローバルな包装ソリューション提供体制の構築を目指しています。
まとめ
製紙業界は、デジタル化の波や環境問題への対応など、さまざまな課題に直面していますが、同時に新たな成長機会も生まれています。
包装材や衛生用品市場の拡大、IoTやAIの導入による競争力強化、そして海外市場への展開など、業界全体が変革期を迎えています。この変化に適応し、持続可能な事業モデルを構築することが、今後の製紙業界の発展につながります。
環境に配慮した製品開発や新素材の実用化に注目することで、製紙業界の未来を見据えた投資や事業展開の可能性が広がるでしょう。