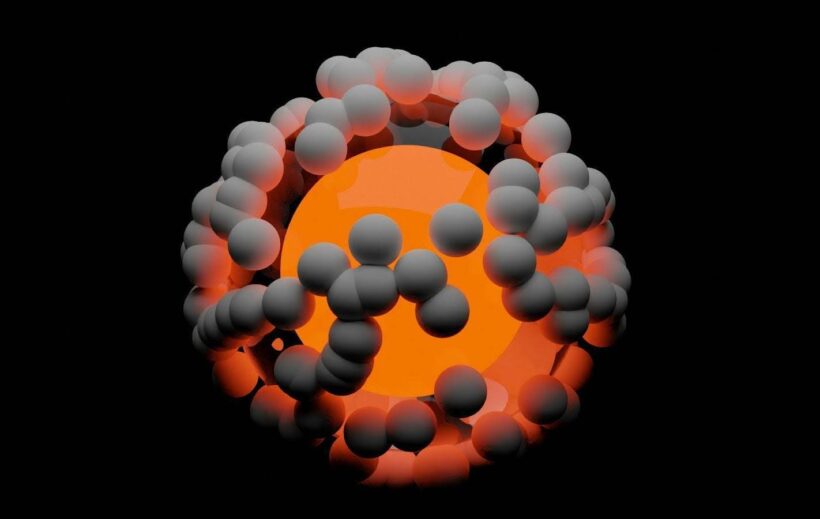Contents 目次
太陽光発電のPPAモデルとは
太陽光発電の導入を検討する際、初期費用の負担が大きな課題となります。PPAモデル(Power Purchase Agreement:電力販売契約)は、この課題を解決する新しい仕組みとして注目を集めています。
PPAモデル(Power Purchase Agreement:電力購入契約) とは、発電事業者が設置・管理する太陽光発電設備から、企業や自治体が長期契約で電力を購入する仕組み です。これにより、設備投資をせずに再生可能エネルギーを調達でき、電気料金の安定化や脱炭素化を推進できる というメリットがあります。
基本的な仕組み
PPAモデルは、施設所有者とPPA事業者の間で交わされる契約に基づいて運用されます。PPA事業者は施設所有者の敷地や建物のスペースに無償で太陽光発電設備を設置し、維持管理を行います。
施設所有者はPPA事業者が設備で発電した電気を使用し、その分の電気料金を支払います。通常の契約期間は10年から20年程度で、契約期間終了後は設備を譲り受けることができます。
自己所有モデルとの違い
自己所有モデルは、企業が自社で太陽光発電システムを購入し、設置・運用する従来の方法です。多額の初期費用とメンテナンス費用が必要となりますが、発電した電気を無料で使用でき、余剰電力を売電することも可能です。
一方、PPAモデルは長期契約で電気を購入する仕組み であり、自己所有モデルとは異なり、設備の所有権はPPA事業者にあります。PPAモデルは初期費用とメンテナンス費用はかかりませんが、発電した電気に対して料金を支払う必要があり、売電はできません。
リースモデルとの違い
リースモデルは、リース事業者から太陽光発電設備を借りて利用する方式です。PPAモデルと同様に初期費用は不要ですが、月々のリース料金として一定額を支払います。
リースモデルと異なる点は、電力の購入が「使用した電力量に応じた従量課金」方式であること で、リースは設備の貸し出しに対する固定料金を支払う点が違います。つまり、PPAモデルが使用した電気量に応じた料金支払いなのに対し、リースモデルは発電量に関係なく固定のリース料金を支払う点が異なります。また、リースでは余剰電力の売電が可能ですが、PPAモデルでは売電できない違いがあります。
PPAモデル注目の背景
世界的な脱炭素化の流れを受けて、PPAモデルによる太陽光発電の導入が急速に広がっています。2022年には世界全体で36.7GWものPPA契約が新たに締結され、2021年と比較して18%以上も市場が拡大しました。また、2008年から2022年までの累計導入量は148GWに達しており、これはフランスの全発電量を上回る規模となっています。
この背景には、企業がRE100やSBTなどの国際的なイニシアチブへの対応を迫られていることがあります。とりわけ米国では、Amazonを筆頭に大手テクノロジー企業がPPAによる再生可能エネルギーの調達を積極的に進めています。例えば、Amazonは2022年時点で24.8GWものPPAを締結しており、これは電力会社を含めても世界第7位の再エネポートフォリオとなっています。
また、Meta(旧Facebook)やGoogleといった企業も、それぞれ2.6GW、1.6GWのPPA契約を2022年に締結しました。このような大手企業の動きは、PPAモデルが再生可能エネルギー調達の有効な手段として認知されていることを示しています。
非FIT時代を迎え、日本国内でも新たなビジネスチャンスとして異業種からの参入が相次いでいます。例えば、関西電力は2023年に再エネ投資会社などと新会社を設立し、リース会社とJFEグループ企業も合弁会社を立ち上げるなど、様々な業界からPPA事業への参入が進んでいます。
PPAモデルの種類
PPAモデルは、発電設備の設置場所によって次の2つに分類されます。
- オンサイトPPA
- オフサイトPPA
それぞれに特徴があり、企業の状況や目的に応じて選択することができます。
オンサイトPPA
オンサイトPPAは、電力を使用する企業の敷地内にPPA事業者が太陽光発電設備を設置し、発電した電気を供給する仕組みです。工場やビルの屋根、駐車場など、未利用のスペースを活用して発電設備を設置します。設備の所有権はPPA事業者にあり、設置後の運用やメンテナンスもPPA事業者が担当します。
企業にとってのメリットは、遊休スペースを有効活用できることに加え、送電網を介さないため送電ロスが最小限に抑えられる点です。さらに、再エネ賦課金がかからないため、一般の電力会社から購入する電気より割安になります。また、災害時には非常用電源としても活用できるため、事業継続計画(BCP)の観点からも有効な選択肢となります。
オフサイトPPA
オフサイトPPAは、企業の敷地から離れた場所にPPA事業者が発電設備を設置し、送配電網を通じて電力を供給する方式です。発電所と需要地が離れているため、一般送配電事業者が管理する送配電網を利用して電力を供給します。
この方式の主なメリットは、企業の敷地内に設置スペースがない場合でも再生可能エネルギーを調達できる点です。また、設置場所の制約が少ないため、より大規模な発電設備を導入することが可能です。さらに、一つの発電所から複数の事業所に電力を供給できるため、複数拠点を持つ企業にとって効率的な再エネ調達手段となります。
太陽光発電のPPAモデルのメリット
太陽光発電のPPAモデルには、企業にとって以下のようなメリットがあります。
- 初期費用を抑えられる
- 電気代が高騰するリスクを回避できる
- メンテナンスをPPA事業者に任せられる
これらのメリットにより、企業は財務面と運用面の両方で負担を軽減しながら、再生可能エネルギーの導入を実現できます。以下では、それぞれのメリットについて解説します。
初期費用を抑えられる
PPAモデルでは、太陽光発電システムの設置に必要な初期費用をPPA事業者が全額負担します。通常、産業用の太陽光発電システムを導入する場合、数百万円から数千万円の投資が必要となりますが、PPAモデルではこれらの費用が不要です。
資金調達の負担がないため、現時点で十分な資金を持っていない企業でも、太陽光発電システムを導入できます。また、投資資金を他の事業活動に振り向けることも可能となり、企業の資金効率を高めることができます。
電気代が高騰するリスクを回避できる
PPAモデルでは、契約期間中の電気料金単価が固定されます。これにより、燃料価格の高騰や市場の変動による電気料金の上昇リスクを回避できます。さらに、PPAモデルで発電された電気には再エネ賦課金がかからないため、通常の電力会社から購入する電気よりも割安になります。
2021年から2022年にかけて電気料金が大幅に上昇したことを考えると、長期間にわたって安定した電気料金を確保できることは、企業の経営にとって大きなメリットとなります。
メンテナンスをPPA事業者に任せられる
太陽光発電システムの保守管理や修理はすべてPPA事業者が担当します。定期的な点検や清掃作業、故障時の対応など、維持管理に関わる作業と費用をPPA事業者が負担するため、企業側の手間とコストを大幅に削減できます。
発電設備の不具合は発電量の低下につながるため、PPA事業者は迅速な対応を行います。また、自然災害による設備の損傷リスクもPPA事業者が負うため、企業は予期せぬ修繕費用の発生を心配する必要がありません。
太陽光発電のPPAモデルのデメリット
PPAモデルはメリットの多い仕組みですが、一方で検討すべきデメリットとして以下があります。
- システムを購入した場合よりも節約額が低い
- 契約期間中の移動や撤去には違約金が発生する
- 設置場所によっては契約できない可能性がある
以降では、これらのデメリットについて解説します。
システムを購入した場合よりも節約額が低い
自社で太陽光発電システムを購入した場合、発電した電気を無料で使用できます。一方、PPAモデルでは使用した電力量に応じて電気料金を支払う必要があります。
そのため、長期的な視点で見ると、自己所有の場合と比べて電気代の削減効果は小さくなります。また、余剰電力を売電することもできないため、収益化の機会も限られています。
契約期間中の移動や撤去には違約金が発生する
PPAモデルの契約期間は一般的に10年から20年と長期に及びます。この期間中、自社都合による設備の移動や撤去は原則として認められず、やむを得ず実施する場合は違約金が発生します。
事業所の移転や屋根の改装工事などで太陽光パネルの移設が必要になった場合でも、契約解除や違約金の支払いを求められる可能性があります。ただし、PPA事業者によっては移設費用を負担するケースもあるため、契約前に詳細な条件を確認することが重要です。
設置場所によっては契約できない可能性がある
PPA事業者は事前審査を行い、太陽光発電システムの設置場所が適切でないと判断した場合、契約を断ることがあります。具体的には以下のような場合に契約できない可能性があります。
- 日照量が不十分な地域
- 塩害や強風などへの特別な対策が必要な場合
- 適切な設置場所を確保できない場合
- 設置容量が少なすぎる場合
- 設置工事やメンテナンスの負担が大きい場合
太陽光発電のPPAモデルがおすすめのケース
太陽光発電のPPAモデルは、特に以下のような特徴を持つ企業での導入がおすすめです。
● 再生可能エネルギーを安価に導入したい企業
初期費用の負担なしで太陽光発電設備を導入でき、発電した電気も電力会社より割安で購入できます。また、再エネ賦課金がかからないため、長期的な視点でも電気料金を抑制することができます。
● 設備の維持管理を任せたい企業
太陽光発電システムの運用やメンテナンス、修理などはPPA事業者が担当するため、専門知識や技術がなくても安心して再生可能エネルギーを導入できます。設備の故障や自然災害による損傷リスクもPPA事業者が負担します。
● 新築または築浅の施設で長期利用を予定している企業
契約期間が10年から20年と長期にわたるため、建物の建て替えや大規模修繕の予定がなく、長期的な施設利用が見込める企業に適しています。設備が契約期間満了後に無償譲渡されることで、その後は電気料金の支払いも不要になります。
PPAモデル事例
PPAモデルは国内外で導入が進んでおり、多くの企業が環境への取り組みとコスト削減の両立を実現しています。ここでは、日本企業と海外企業の具体的な導入事例を紹介します。
日本の導入事例
ニトリホールディングスは、店舗及び物流倉庫の屋根を活用した大規模なPPAプロジェクトを開始しました。このプロジェクトは2022年度からスタートし、30拠点程度への導入を予定しています。2030年度までに設置可能な拠点に順次拡大することで、発電容量は総計80MW規模となり、年間発電量は10万MWhを超える見込みです。これは一般家庭約23,000世帯分の年間電力使用量に相当する規模です。
ニトリホールディングスはTCFD提言に賛同し、環境に配慮した経営を推進する方針を表明しています。2030年度までに2013年度比で温室効果ガス排出量を50%削減し、2050年度までにカーボンニュートラルを達成することを目標としています。PPAモデルの導入により、化石燃料価格高騰の影響を受けにくい安定的なエネルギー調達構造の実現を目指しています。
海外の導入事例
トヨタ自動車の北米統括会社であるToyota Motor North America(トヨタモーターノースアメリカ)は、Clearway Energy Groupと2回目となるバーチャルPPA契約を締結しました。この契約では、ミシシッピ州デソト郡のワイルドフラワープロジェクトから80MWの電力を購入します。この発電量は、トヨタの北米における電力使用量の約8%に相当します。
トヨタはグローバル環境チャレンジ2050の一環として、事業活動におけるカーボンニュートラルの実現を目指しています。この契約により、2035年までの米国の製造施設でのカーボンニュートラル達成に向けた大きな一歩となります。また、プロジェクトを通じて地域社会への貢献も実現し、建設時には数百人の雇用を創出するといった副次的な効果も期待されています。
まとめ
PPAモデルは、初期費用ゼロで太陽光発電システムを導入できる新しい仕組みとして注目を集めています。企業は発電設備の設置場所を提供し、その見返りとして再生可能エネルギーを電力会社よりも安価に調達できます。また、設備のメンテナンスや管理もPPA事業者が担うため、運用面での負担も軽減できます。
一方で、10年から20年という長期契約が必要なため、導入を検討する際は自社の事業計画との整合性を十分に確認する必要があります。世界的に見ると、AmazonやGoogleといった大手企業が積極的にPPAモデルを活用しており、日本国内でもニトリホールディングスなど、導入事例が増加しています。企業の脱炭素化とコスト削減の両立を実現する手段として、PPAモデルの重要性は今後さらに高まっていくでしょう。