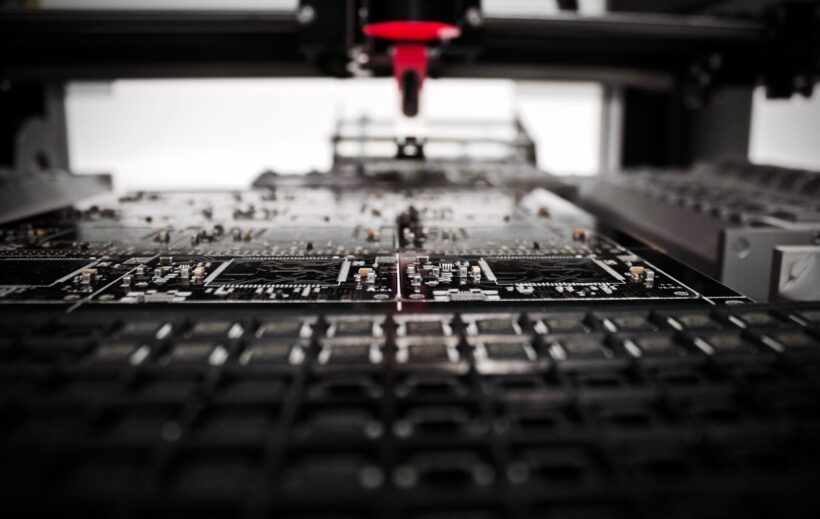Contents 目次
マイクロLEDとは
マイクロLEDは、照明や信号などに利用されているLED(発光ダイオード)を超微細なサイズに小型化した、次世代ディスプレイ技術です。赤・緑・青(RGB)の3色のマイクロLEDを1組として1画素を構成し、これらを高密度に配置することで鮮明な映像を実現します。
現在、大型テレビやデジタルサイネージといった従来のディスプレイ分野での実用化が進んでおり、ソニーやSamsungが業務用ディスプレイの販売を開始。さらに、スマートウォッチなどのウェアラブルデバイス、車載ディスプレイ、ARグラス向けディスプレイなど、幅広い分野での活用が期待されています。
マイクロLEDが注目される理由
マイクロLEDは、従来のディスプレイ技術が持つ課題を解決できる可能性を秘めています。バックライトを必要としない自発光型の構造により、高輝度と高コントラストを実現。液晶ディスプレイの課題だった応答速度の遅さや光漏れの問題も解消します。
また、有機ELディスプレイで懸念される焼き付きや劣化も起こりにくく、消費電力も少ないため、バッテリー駆動のモバイル機器にも最適です。薄型・軽量で柔軟な形状にも対応できることから、新たなディスプレイ用途の開拓も進んでいます。
マイクロLEDと有機EL・液晶の違い
マイクロLED、有機EL、液晶には、それぞれの特徴に応じたさまざまな違いがあります。
主な違いを以下の表にまとめました。
| マイクロLED | 有機EL | 液晶 | |
| 発光方式 | 自発光素子であるLEDで画素を構成 | 自発光素子(有機材料)で画素を構成 | 白色発光のLEDのバックライトでパネル全体を均一に照らし、液晶シャッターで調整 |
| 輝度 | ◎(非常に高い) | △(低い) | ◯(高い) |
| 応答速度 | ◯(速い) | △(遅い) | ◯(速い) |
| 焼き付き | ◯(起こりにくい) | △(起こりやすい) | △(起こりやすい) |
| 耐久性 | ◎(非常に高い) | △(低い) | ◯(高い) |
| 消費電力 | ◎(非常に低い) | ◯(低い) | △(高い) |
| 生産性 | ×(非常に低い) | ◯(高い) | ◯(高い) |
有機ELとの違い
マイクロLEDと有機ELは、どちらも自発光方式ですが、その特性には大きな違いがあります。最も顕著な違いは、発光素子の材料にあります。有機ELは有機材料を使用しているため、経年劣化や焼き付きが起こりやすく、長期的な耐久性に課題があります。そのため、焼き付きや画質劣化を防ぐために輝度を抑える必要があり、特に明るい場所での視認性に難があります。
一方、マイクロLEDは無機材料で構成されているため、焼き付きの心配が少なく、高輝度での表示が可能です。また、消費電力の面でも、カラーフィルターを必要としないマイクロLEDの方が効率的な発光を実現できます。
液晶との違い
マイクロLEDと液晶では、映像を表示する仕組みが根本的に異なります。液晶は、バックライトの白色光を液晶シャッターで調整し、カラーフィルターで色付けする方式です。この構造では、完全な光の遮断が難しく、黒の表現が不完全になりがちです。また、液晶分子の動きに時間がかかるため、動きの激しい映像で残像が発生します。
一方のマイクロLEDは、各画素が独立して発光するため、完全な黒表現が可能で、応答速度も速いため残像の問題もありません。さらに、バックライトや偏光板などの部品が不要なため、薄型化が可能で消費電力も抑えられるという利点があります。
マイクロLEDのメリット
マイクロLEDは、次世代ディスプレイ技術として数々の革新的な特徴を備えています。高輝度と高コントラスト比による圧倒的な映像表現力、スポーツ中継などの動きの速い映像もクリアに表示できる高速応答性、そして有機ELや液晶の半分以下という省エネルギー性能を実現。
さらに、フレキシブルディスプレイや透明ディスプレイといった新しい表示デバイスへの応用も期待されています。
高輝度・コントラスト比が高い
マイクロLEDの高輝度・高コントラスト比は、その独自の発光方式に由来します。各画素が独立して発光する自発光型の構造により、必要な部分だけを適切な明るさで光らせることが可能です。特に黒の表現において、光を完全に遮断できるため、極めて高いコントラスト比を実現します。
この特徴は、日中の明るい場所でも鮮明な映像表示を可能にし、屋外デジタルサイネージやスマートウォッチなど、さまざまな環境で使用されるデバイスに大きなメリットをもたらします。また、HDR(ハイダイナミックレンジ)コンテンツの視聴でも、明部から暗部まで豊かな階調表現を実現し、より臨場感のある映像体験を提供します。
応答速度の向上と視認性の強化
マイクロLEDの応答速度の速さは、各LED素子が独立して瞬時にオン/オフを切り替えられる特性によるものです。液晶ディスプレイでは、液晶分子の物理的な動きに時間がかかるため、動きの激しい映像で残像が発生するという課題がありました。
しかし、マイクロLEDはナノ秒レベルでの高速応答が可能です。この高速応答性により、スポーツ中継やアクション映画、ゲームなどの動きの激しいコンテンツでも、残像やブレの少ない鮮明な映像表示を実現しています。VRやARなどの没入型コンテンツでも、視認性の高い映像表示が可能となり、酔いの軽減にも貢献します。
省エネルギーと長寿命
マイクロLEDは、その効率的な発光方式によって消費電力を抑えています。液晶ディスプレイやRGBW方式の有機ELテレビで必要とされるカラーフィルターが不要で、光の損失を最小限に抑えられます。2012年にソニーがCES(コンシューマー・エレクトロニクス・ショー)で発表した55インチモデルでは、同サイズの液晶テレビの半分以下となる平均70Wの消費電力を実現しました。
この低消費電力特性は、特にモバイル機器で大きな価値を発揮します。スマートフォンでは、その消費電力の多くをディスプレイが占めているため、マイクロLEDの採用によってバッテリー持続時間の大幅な改善が期待できます。また、無機材料を使用しているため、有機ELのような経年劣化も少なく、長期間の使用が可能です。
フレキシブルディスプレイや透明ディスプレイへの応用
マイクロLEDの小型・軽量という特性は、革新的なディスプレイ形態を可能にします。2024年にSamsungが発表した透明マイクロLEDディスプレイは、あたかもガラスのように透明でありながら、高品質な映像表示を実現。また、極小サイズのLEDチップを柔軟な基板に実装することで、曲面ディスプレイやフレキシブルディスプレイの開発も進められています。
これらの新しいディスプレイ形態は、従来のフラットパネルの概念を超えた応用を可能にします。例えば、建物の窓ガラスやショーウィンドウに組み込む透明ディスプレイ、腕に巻きつけられるウェアラブルデバイス、車のダッシュボードに沿った曲面ディスプレイなど、革新的な用途が期待されています。
マイクロLEDのデメリット
マイクロLEDの実用化における最大の課題は、製造プロセスの複雑さと高コストです。4Kディスプレイの製造には約2,400万個のLEDチップが必要で、これらを精密に配置する必要があります。現在主流の「Pick and place」方式では、1個ずつLEDチップを配置するため、製造に膨大な時間がかかります。この結果、89インチモデルで約8万米ドル、110インチで約15万米ドルという高価格になっています。
各メーカーは一括形成技術や「マストランスファー」など新技術の開発を進めていますが、4Kディスプレイ1枚の製造に5日程度必要とされ、量産化への道のりはまだ遠い状況です。
マイクロLEDの市場規模
矢野経済研究所の2024年の調査によると、マイクロLEDディスプレイの世界市場は2024年に前年比297.6%の24万4,000台に達すると予測されています。特に3インチ以下の小型電子デバイスやスマートウォッチ向けの需要が拡大傾向にあり、2031年には2,138万台まで成長すると見込まれています。
注目すべき動向として、AR端末向けのLEDoS(LED on Silicon)マイクロLEDディスプレイの採用拡大があります。従来の超小型LCDに代わり、高輝度・低消費電力のLEDoSは、透明グラスに画面を表示するAR機器に特に適しているとされています。
また、製造技術開発も活発化しており、東レがレーザー転写用材料の開発に成功し、信越化学工業は移送部品および移送装置の開発を続けラインナップを拡大しています。ブイ・テクノロジーやサムコなどの製造装置メーカーも参入し、京セラやシャープなど大手電機メーカーも開発を本格化させています。特に、北米のIT大手企業による技術獲得のための企業買収や事業提携も増加しており、市場の急成長を見据えた開発競争が加速しています。
主要メーカーの動向(Apple、Samsung、ソニーなど)
マイクロLED開発において、各社が特徴的な戦略を展開しています。Appleは長年スマートウォッチ向けマイクロLEDの開発を進め、総額30億ドル以上を投資。2014年にはマイクロLEDベンチャーのLuxVueを4億2,000万ドルで買収するなど積極的な展開を見せましたが、2024年、技術的課題とコスト面から開発プロジェクトの中止を決定しました。
Samsungは大型ディスプレイ分野に注力し、2021年にはマイクロLEDテレビの販売を開始。2024年1月のCES 2024では透明マイクロLEDディスプレイを発表するなど、革新的な製品開発を続けています。
ソニーは業務用途に特化し、2016年に業務用マイクロLEDディスプレイを発売。その後、映画撮影用のバーチャル背景システムとしてCrystal LEDを展開し、製作期間を半減できる新しいワークフローを実現しています。
また、画像センシング技術の開発にも注力し、リアルタイム3Dセンシング技術や偏光センサーの開発を進めるなど、マイクロLEDの性能向上に寄与する技術開発を続けています。
| メーカー | 戦略・動向 |
| Apple(米国) | スマートウォッチ向け開発を進めていたが、2024年に開発中止を決定。 |
| Samsung(韓国) | 大型ディスプレイ特化。テレビ・デジタルサイネージ向けに透明マイクロLEDを発表。 |
| ソニー(日本) | 業務用・映画向けのCrystal LEDで高評価。バーチャルプロダクション技術にも活用。 |
| 京セラ(日本) | 車載・ARグラス向けの超小型マイクロLED開発に注力。 |
| BOE(中国) | スマートウォッチ・ARデバイス向け。低コスト量産を目指す。 |
| Innolux(台湾) | 半導体製造技術を応用し、コスト削減を推進。量産化に挑戦。 |
マイクロLEDの製造業への影響
マイクロLED技術は、ディスプレイ製造に大きな変革をもたらしています。従来のLED製造とは異なり、半導体製造に近い高度な製造プロセスが必要となり、クリーンルームの基準も厳格化されています。
製造装置メーカーも新たな市場機会を見出し、先にも触れたとおり、東レはレーザー転写用材料を、信越化学工業は移送部品の開発を進めるなど、サプライチェーン全体が進化しています。
特に、製造プロセスのデジタル化や自動化、AI技術の活用によって、従来の製造業の枠を超えた技術革新が加速しています。こうした変化は、新たな技術開発投資や人材育成の必要性を生み出し、製造業全体の高度化を促進しています。
まとめ
マイクロLEDは、高輝度、高コントラスト、低消費電力、長寿命といった優れた特性を持つ次世代ディスプレイ技術として注目を集めています。2024年の世界市場は前年比297.6%の24万4,000台と急成長を遂げ、2031年には2,138万台規模まで拡大すると予測されています。また、応用分野もテレビやスマートウォッチから、AR/VRデバイス、自動車用ディスプレイまで多岐にわたります。
一方で、製造工程の複雑さやコストの高さなど、実用化に向けた課題も存在します。しかし、各メーカーの技術革新や新たな製造プロセスの開発により、これらの課題は着実に解決に向かっています。マイクロLED技術は、単なるディスプレイの進化にとどまらず、製造業全体の技術革新を促進し、新たな市場機会を創出する可能性を秘めています。